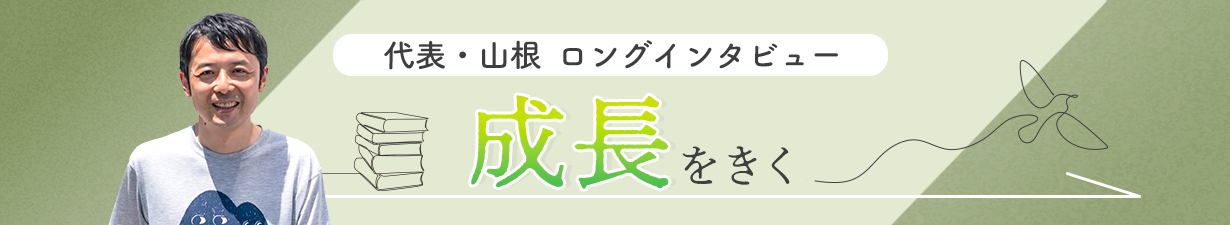Mogicはかんがえる
少人数+ソフトウェア+サーバやロボットの組み合わせで
新しい時代の会社経営を進めています。
そのプロセスの一部をこのコーナーでお伝えできればと思っています。
2025.05.19
余白というセーフティネット
社内あちこちから「余白を作って」「余力を考えて」「余裕を持たせて」と聞こえてきます。
もちろん精神衛生からいえば、ゆとりはいいものです。
しっかりと準備して、じっくりと進められますから。
ゆとりがあることで、自分たちらしく仕事を進められる。
なんて理想論をいうこともありますが、本質は現実的な対処から導かれたものです。
なぜ余白を作るのか?それがはたらく人だけのためじゃないとしたら?
答えは、組織の運営を自律的かつ自動的に補正するため。
そのための理論的な土台としてパーキンソンの法則を利用しています。
まずはイギリスの政治学者が提唱した有名な法則から
ーーーーー
パーキンソンの法則
https://w.wiki/mP8
元々は、英国の官僚制を俯瞰した結果として、官僚達が自分達の相互利益のために、仕事を作り出して行政運営を実施し、それに見合う部下を新たに雇い入れ、予算が得られれば得られた分だけ、官僚達が増長してゆく様子を示した法則であった。
パーキンソンの法則を一言で言うと、例えば、役人の数は、仕事の量とは無関係に増え続けるという説明が可能である。
具体的な法則としては
第1法則
仕事の量は、完成のために与えられた時間を全て満たすまで膨張する
第2法則
支出の額は、収入の額に達するまで膨張する
以上の2つから成る。
ーーーーー
端的にまとめると「ほっとけば、あればあるほど使っちゃう」です。
もう少し会社の業務によせてパーキンソンの法則を改変してみます。
第1法則
個人において、仕事の量は勤務時間を全て満たすまで膨張する
第2法則
会社において、予算の費用額は予算の売上額に達するまで膨張する
この第1法則から導かれる予想解は
・最初は仕事量を抑えるが、経過するほど残業の確率が上昇する
・勤務時間がある限り、本当はもうしなくていい仕事を見直すことはない
とか
第2法則から導かれる予想解は
・売上が未達であっても、費用は予定どおりかさ増しされていく
・手元にお金のある限り、本当はしなくてもいい仕事を見直すことはない
とか
これら無自覚な膨張の危険性を考慮するなら、満杯であふれる前にリミッターをかけておくのが最善です。
今の器であふれるのなら、わざと少し小さい器を用意する。
小さい器が先に満ちることで、警報を鳴らすことができる。
普通の器が満杯になるまでに時間があれば、対策をたてやすい。
個人の家計でいえば「給料日のすぐ後に天引きして預金を積みたてる方法」に似ています。
天引きされたのちの給与、つまり小さい器でその月の生活をやりくりする。
小さな器でやれているうちは、うまくいっているとみなせる。
もしも小さな器からこぼれたなら、何かがおかしいと気がつく。
突発的なことで仕方ないなら、積みたてた余力をつかう方法もあるしと。
個人の仕事でいえば、はじめに「余力を考えて」予定を組んでおくと力を使いはたす前に誰かが気づいてくれる。
会社のお金なら、あらかじめ「余裕を持たせて」おくことですっからかんになる前にいらない仕事をやめられる。
そうです、余白とは単なるのんびりした雰囲気や働き方改革のためではないのです。
経営の観点でみればセーフティネットが立ちあがる装置、しかも組織というネットワークが自律的かつ自動的に補正をかける起点となっているのです。
最新記事
代表インタビュー
月別アーカイブ
- 2025年05月
- 2025年04月
- 2025年03月
- 2025年02月
- 2025年01月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年09月
- 2024年08月
- 2024年07月
- 2024年06月
- 2024年05月
- 2024年04月
- 2024年03月
- 2024年02月
- 2024年01月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2023年08月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2023年04月
- 2023年03月
- 2023年02月
- 2023年01月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年09月
- 2022年08月
- 2022年07月
- 2022年06月
- 2022年05月
- 2022年04月
- 2022年03月
- 2022年02月
- 2022年01月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2021年08月
- 2021年07月
- 2021年06月
- 2021年05月
- 2021年04月
- 2021年03月
- 2021年02月
- 2021年01月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年09月
- 2020年08月
- 2020年07月
- 2020年06月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2020年03月
- 2020年02月
- 2020年01月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年09月
- 2019年08月
- 2019年07月
- 2019年06月
- 2019年05月
- 2019年04月
- 2019年03月
- 2019年02月
- 2019年01月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年09月
- 2018年08月
- 2018年07月
- 2018年06月
- 2018年05月
- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年03月
- 2017年01月
- 2016年11月
- 2016年06月
- 2016年03月
- 2015年12月
- 2015年04月
- 2014年07月
- 2014年05月
- 2013年06月
- 2013年03月
- 2012年12月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月